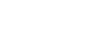ライラット系第三惑星マクベス。無数にある採掘場からの鉱物資源に恵まれ、盛んな加工業・製造業で発展したこの工業都市惑星は、工業の中心地として長くライラット系全体を支えてきた。
先の大戦ではアンドルフ軍に占拠され軍事基地と成り果ててしまったが、その大戦が終結し解放されたマクベスは、かつての健全な賑わいを取り戻しつつあった。
一方で、そのマクベスを解放した戦争終結の立役者、今やライラット系の英雄と持て囃される雇われ遊撃隊スターフォックスの状況は芳しくない。彼らが命を賭して勝ち取った平和は傭兵から血生臭い仕事をことごとく奪い、結果としてスターフォックスは日に日に瀕する苦しい財政状況を強いられている。有り体に言えば、仕事もないし金もない二重苦だった。
この状況に責任を感じてか、フォックスは「軍属を受け入れていたら良かったかな……」などと思ってもいないことをぼやきつつ、とても傭兵向きではない求人広告を眺めるのが日課になっているほどだ。一度はその中にいかがわしい求人が紛れ込み、渋い顔をしながらも基本給の欄から目を離せずにいるフォックスの頭をファルコが引っぱたいたこともあった。リーダーが金に困って身売りなど、ファルコはもちろんのことスリッピーとペッピーが許すはずがない。
細々と雑用まがいの仕事を受けて何とか食い繋いでいるフォックスたちに、ある日一つの依頼が舞い込んだ。戦争終結からちょうど三年が経った時のことだ。
ペパー将軍直筆の署名とともに「くれぐれも秘密裏に」と届けられた依頼の内容は、件の惑星マクベスの調査だった。一大工業都市として今まさに復興中のマクベスでは、最近どうもきな臭い動きがあるらしい。未だ点在するアンドルフ軍の補給基地の跡地の一つにならず者が集まってレジスタンスを名乗っているだとか、連中は志半ばで倒れたアンドルフの意志を継いで再び戦争を起こそうとしているだとか、不穏でありふれた噂が囁かれているとの話だ。この手の噂は戦争終結後に掃いて捨てるほど涌いたものだが、ペパー将軍直々の依頼となると話は変わってくる。軍のトップの目から見て、看過できない噂だということだからだ。
もちろん、フォックスはこの依頼を二つ返事で引き受けた。平和のため、それから報酬のために。
「けどなあ……マクベスか……」
出撃前のブリーフィングで、フォックスは腕組みをして沈痛な面持ちで呟いた。
今回の作戦のメンバーはファルコにスリッピー、それからフォックスだ。ペッピーは緊急事態が発生した時に備えてグレートフォックスで待機、スリッピーはターゲットが保有しているとされる武器の分析のために同行、ファルコは言わずもがなである。
ブリーフィングに同席する二人は、なんとも煮え切らない顔をしているフォックスを見て首を傾げている。無言で「どうした?」と訊かれていることはわかっているが、フォックスの返事もまた無言だった。
フォックスほど嗅覚が鋭くないファルコやスリッピーには伝わらないだろうが、マクベスは工業都市である。今日の繁栄に至るまでの歴史や血塗られたマニュアル、重ねられた法改正に加えて近隣惑星であるコーネリアの援助もあり、最近は惑星の環境維持にも力を入れていると聞く。しかしどうしても、産業公害は免れない。騒音や臭気のことを殊更に言うのはその環境で働く者への侮蔑と捉えられかねない風潮があるが、イヌ種やキツネ種などの鼻が利く種族からすれば正直に言ってマクベスは物凄く煙たいし臭いのだ。
アーウィンで空にいる時はいい。地表でもランドマスターの中なら耐えられる。だがそんなものに乗ったまま敵の本拠地に突っ込むわけにはいかない。今回の任務は殲滅ではなく敵情視察と交渉のため、必然的に生身でマクベスを歩かざるを得ないのだ。
その臭いには目を瞑るついでに鼻を塞ぐとしても、マクベスの問題はそれだけではない。
定住するイヌ系の種族が多いコーネリアに対して、ライラット系以外からも多くの労働者が集まるマクベスは種族の坩堝である。しかしその雑多さは、他種族への寛容に直結しない。種族差に根ざす感覚や文化の違いが軋轢を生み、無計画に乱立するコロニーは地区を不必要に分断する。イヌ種の支配惑星と揶揄されるコーネリアの民が概ね異種族に好意的であるのに対して、仕事を求める何者をも拒まないと喧伝するマクベスで種族間の軋轢が絶えないのは、なんとも皮肉な話である。
公害問題に加えて、治安も悪い。そして肉体労働が貴ばれ、屈強さこそが正義とされるのがマクベスだ。お世辞にも筋骨隆々とは言えないスターフォックスの面々は、見た目からして侮られるのが目に見えている。
だがこれは仕事だ。選り好みはしていられない。両拳を握りしめて気合を入れ直したフォックスは、まだ不思議そうに首を傾げているファルコとスリッピーの顔を見渡すと、リーダー然とした声を張り上げる。
「最終確認だ。今回の任務はマクベスにおける不穏分子の調査および交渉、対象のアジトへ真正面から乗り込む。ターゲットが敵対的である場合は応戦を許可、自分とチームの命を最優先に行動せよ。……だが地上での戦闘はどんなに上手くやろうと負傷を免れない。出来るだけ穏便に済ませよう。ファルコ、挑発されても乗るんじゃないぞ」
「へいへい、リーダー様の仰せのままに」
「スリッピーも。相手を刺激するような発言は控えてくれよ」
「わかったよー」
「よし。じゃあ、行くぞ!」
フォックスの号令で、三人はブリーフィングルームを飛び出した。
俊足を誇るフォックスが先頭を、ファルコがその後ろにぴったりと続き、二歩遅れてスリッピーが付いていく。
この数時間後、敵のアジトのど真ん中で激昂したフォックスが大暴れし、スリッピーが頭を抱え、ファルコが絶叫する羽目になるのだが、この時はそんな大惨事が繰り広げられることになろうとは、誰一人夢にも思っていなかった。
問題なくマクベスに着陸した一行は、アーウィンをコーネリア軍基地に預けて徒歩でターゲットのアジトへ向かった。
今回の任務に際して、フォックス達には武器製造工業における第三者監査機関の職員という仮初の肩書がコーネリア軍から与えられていた。今回のターゲットは表向きはアンドルフ軍の兵器製造工場跡地を利用した産業火薬製造会社を名乗っている。そこで何の戦闘力もない抜き打ち監査員としてアジトを訪れ、油断を誘った上で的確に敵情を把握しようというわけだ。
しかしそんな小手先が通用したのは入り口までだった。建物内に踏み入ったフォックス達の案内役を買って出た大柄なロバの男は、彼らが職員IDを提示するなり慇懃無礼に嘲笑した。
「アンタらの正体も目的もわかっておりますとも。お互い下手な嘘はやめましょうや」
バレているなら、嘘を続ける理由もない。フォックスたちは肩を竦め、大人しく男に連れられて建物の奥へ奥へと進んでいった。
これだけでもわかった事は多い。この『会社』は軍からの派遣を警戒し、対応する理由がある。軍が正式発行した正真正銘正規のIDを一目で切り捨てたことから、この内偵が何らかのルートで漏れていた可能性も考えられる。あるいは、フォックス達の出で立ちから『あの』スターフォックスであると看破したのかもしれないが、多くの民衆にとってスターフォックスの名が示すのは空を駆けるアーウィンとそこに描かれた赤のロゴマークである。一般向けの報道にはほぼ載らないフォックス達の顔が割れているとすれば、それなりの情報網を持っていることが読み取れるだろう。
フォックスと同じ結論に辿り着いたのか、ファルコは腕組みをして警戒心を露わにしている。スリッピーもいつになく真剣な目で周囲の様子をつぶさに窺っており、この場所が良心的な会社ではないことはほぼ確定したようなものだ。
三人が男に連れられて辿り着いたのは、客を通す応接室とは程遠い、雑多に物が置かれた広い倉庫のような場所だった。誘い込まれているのは承知の上だったが、ここまであからさまだと笑ってしまう。実際にファルコが小さく鼻で笑うものだから、フォックスは視線で彼を咎めなければならなかった。
白熱灯で煌々と照らされた倉庫内にはコンテナが散乱していて、その中には銃を中心とするお手軽な兵器がこれでもかと詰め込まれている。スリッピーが小声で「アンドルフ軍のものじゃない。粗悪なコピーだね」とフォックスに耳打ちした通り、とても良質とはいえないことは素人のフォックスでも見て取れた。
ペパー将軍が危惧していたのは、この『会社』の皮を被った集団がアンドルフ軍の残党ではないかということなのだろうが、これまでの情報から考えてその点に関しては杞憂と言えよう。やっている事は褒められたものではなかったが、アンドルフ軍の技術力は本物だった。それを正しく引き継いでいるなら、このような粗悪品の山が生まれることはなかったはずだ。
だがアンドルフ軍とは関係ないだけで、危険であることは疑うべくもない。今フォックス達の視界に入るあらゆる武器は、産業火薬工場には決して必要がないものだ。それに敵意や害意がなければ、下卑た笑みを浮かべる大勢の中へ客人を放り込むような真似はしないだろう。
だだっ広い倉庫の真ん中で案内役の男と対峙するフォックス達を、数十人もの屈強な男たちがずらりと取り囲む。どうやらアポなしの訪問が随分と不興を買ったようだ。尊大な態度で肩を竦めるファルコ、身を縮めながらも緊張した面持ちで周囲を見据えるスリッピーの二人を庇うように前に立ち、フォックスは男に向かって口を開く。
「俺たちは戦いに来たわけじゃない。お前達がこの惑星にとって脅威となるか否か、ただ確認に来ただけだ。もう一度言う、こちらに戦闘の意思はない」
「キツネの癖に囀るじゃねえか、オトモダチのトリに習ったか? こっちは全部知ってんだよ、コーネリアのイヌどもの腰巾着が。権力をカサに善良な一市民の会社を蹂躙して楽しいのかァ、おい!」
返ってきたのはこの通り、直球の侮蔑と大勢の嘲笑だ。慇懃無礼の慇懃部分をかなぐり捨てた男が吼え、バックコーラスのように下卑た笑い声が響き渡る。これでは当初の目的である『平和的な交渉』など望むべくもない。
ファルコもスリッピーもこの時点で荒事が避けられないことを覚悟していたが、フォックスだけはまだ話し合いでの解決を諦めていないようだった。あからさまに馬鹿にされながらも、真摯な態度で男とその後ろに控える大勢に向き合っている。だが真面目を具現化したようなフォックスのその態度は、自称『善良な一市民』たちが燻ぶらせる侮蔑と嘲笑という火に油を注いだだけだった。
そこからはありとあらゆる罵詈雑言がフォックスに投げつけられた。
悪知恵だけの卑怯者、口しか進化しなかった劣等種、発展途上惑星の畜生、イヌとネコの庶子、出来損ないのイヌ、イヌ種に飼い慣らされたペットちゃん等々――。
よくもまあこれだけのバリエーションを用意したものだと感心するほどの罵倒を並べられても、フォックスは涼しい顔をしていた。
イヌ種の近縁種であるキツネ種は、常に彼らと比較されてきた歴史を持つ。実情を知りもしない他種族や驕り高ぶったイヌ種、そして劣等感で腐ったキツネ種自身が、キツネ種に対して不当な評価を下すのは現代でも珍しくないことだ。コーネリアに一大都市を築いたイヌ種に対して、辺境惑星パペトゥーンを主な縄張りとするキツネ種を、田舎者の劣等種だと謗る者は少なくない。目の前に立つこのロバの男も、その類というわけだ。
卑劣な差別意識に満ちた暴言を、しかしフォックスは平然と聞き流している。我慢しているだとか、怒りを堪えているだとか、そんな様子さえ全くない。まるで聞こえていないかのように粘り強く交渉を続ける様に、後ろに控えたファルコは内心舌を巻いていた。思えば常の依頼において取引先との交渉にはフォックスが単身で出向くことが多く、ファルコがその姿を目の当たりにする機会は今までなかった。普段は青臭い正義感を抱えた甘ちゃんの子狐と思わされているだけに、こうして頼もしい姿を見せられると胸に迫るものがある。
しかしファルコの感傷は、それから数分も経たないうちに粉々に砕け散った。
嫌味も皮肉もまるで通じないことに腹を立てたのか、男はその矛先をファルコへ向けたのだ。飛んできたジャブ程度の罵倒をファルコは腕組みしたまま肩を竦めて流したが、とても流せなかったのは隣のフォックスから一瞬にして沸き立った殺気の方である。
ファルコに向けられた罵倒に対し、フォックスは明らかな苛立ちを見せていた。数秒前まで穏やかに相手の目を見つめていた瞳が今は不穏に眇められ、射貫くような視線を投げている。口元に浮かんでいた笑みは完全に消えており、鼻先に寄った皺に引っ張られてひげの毛先がひくひくと揺れていた。
先ほどまでの完璧なポーカーフェイスはなんだったのかと、ファルコは愕然とする。見るからに怒り心頭なフォックスの様子がたいそうお気に召したのか、男は下卑た笑いで唇を歪め、悪し様にファルコを、ついでのようにスリッピーをも罵り始めた。みるみるうちにフォックスの顔の皺が深くなり、遂には口元から白く鋭い牙が覗く。その牙の合間を縫って吐き出された浅く長い呼吸音が、ファルコには着火済みの導火線の音に聞こえてならなかった。
マズい。止めるべきだ。
本能的にそう察したファルコが腕組みを解いたその瞬間、フォックスは警告もなく一足飛びに間合いを詰め、男のみぞおちに蹴りを叩き込んでいた。
一切の躊躇なく繰り出されたフォックスの渾身の一撃は、的確に男の臓腑を抉ったらしい。下卑た笑みが苦痛に歪み、くの字に折りたたまれた巨体は濁った呻き声と共に崩れ落ちた。突然の出来事に誰もが反応できずにいる中、汚らしい嗚咽が静寂を割く。情けない呻き声を漏らし続けるそれを見下ろしたフォックスは、今しがた凶器として使った足の先でトントンと床を蹴っていた。次の獲物を探しながら軽やかに、準備運動でもするかのように。
後ろに控えたファルコの位置からは、当然フォックスの表情は窺えない。だがその背中で揺れる尻尾は雄弁に感情を語っており、彼の怒りが微塵も治まっていないことは顔など見なくてもよくわかった。
場は急速にざわつきを取り戻し、取り巻きの誰かが悲鳴じみた声を上げたのを皮切りに、野太い怒号が渦を巻く。怯えや恐怖、それらを覆い隠す薄っぺらな怒りが、一斉にフォックスを取り囲んだ。
「この……ッ! クソガキがァ……ッ!!」
後はもう、野となれ山となれだ。いきり立って突撃してくる武装集団に、フォックスは怖気づくどころか興奮して毛を逆立てている。ゆらりと大きく揺れる尻尾が楽し気にすら見えて、ファルコはぞっとして彼の背中から視線を逸らした。視界の隅で喉から唸り声を上げて敵陣に飛び込んでいくフォックスを捉えるなり、ファルコは身を翻す。事態に付いていけず慌てふためいているスリッピーの尻を蹴り上げ、その首根っこを引っ掴んだ。見た目よりは軽いスリッピーの巨体を半ば引きずるようにして、ファルコは近くのコンテナの影に身を隠す。
ここから事態をどう収拾するべきか、考えなくてはならない。
「なーにが『穏便に済ませよう』だ! 挑発に乗るな? ハッ、どの口が言ってんだあんのアホギツネ……!!」
万感の思いが込められたファルコの絶叫は、すっかり暴徒と化した武装集団の怒号や銃撃の音に搔き消された。聞いてくれたのは一緒に退避中のスリッピーだけだ。
そして件のフォックスはといえば、今まさに勃発した大乱闘の中心で牙をむき出しにして大暴れの真っ最中だった。いつもは腹が立つくらいキラキラと輝く緑の瞳が怒りに燃えて見開かれており、普段のいかにもな好青年の爽やかさなど見る影もない。
「ああなったフォックスは止まらないんだよねえ……」
衝撃に煽られて吹き飛びかけた帽子を軽々キャッチしながら、スリッピーは暢気に嘆息している。その胸倉に掴みかからんばかりの勢いで、ファルコは苛々と食って掛かった。
「マジでどうしちまったんだ、ウチのリーダーは! ここにゃフサフサのヤツらにだけ効く興奮剤でも撒かれてんのか?!」
「あぁ、ううん、えーっとぉ……。そっかあ、ファルコは見るの初めてかあ……」
詰め寄るファルコの嘴を控え目に押しのけながら、スリッピーは困惑して視線を逸らす。大きな目が絶賛大暴れ中のフォックスと目の前のファルコの間を行ったり来たりと不安定にさまよった。何と言ったらいいものかと迷いに迷っているらしいスリッピーだったが、背後でどんどん酷くなる喧噪も相まって観念したのか、ようやく重い口を開く。
「おかしくなったわけじゃないよ。フォックスはアカデミーの時からそうなんだ。仲間や友達を貶されると、我を失っちゃうっていうかさ」
「アイツが身内贔屓の甘ちゃんなのは知ってるが、限度があるだろ! 第一、俺やお前にクソみてぇな悪口が浴びせられたことなんて、これまでにも散々あっただろうが」
「たぶんそれ、空にいる時だったんじゃない? 操縦桿を握るフォックスが冷静さを失ったことはないでしょ?」
「ゴツイ乗り物に乗って気をデカくしておかしくなる奴はごまんといるが、アイツは逆で乗るとマトモになるってか?」
そいつは傑作だなとファルコが鼻で笑えば、スリッピーは大真面目に頷いて、ちらりとフォックスの方に視線をやる。
「ああなったらもう、馬鹿にして来た奴を全員倒すまで落ち着かないよ」
そう言って両手を上げてお手上げポーズを取るスリッピーはすっかり傍観、待ちの姿勢に入っている。フォックスが万一にもしくじるとは思っていないようだ。
確かに、数十人はいたはずのごろつきどもは軒並み沈められ床に伏している。残っているのは数人、それもだいぶ戦意喪失しているようで逃げ腰だ。対してフォックスの方はと言えばゆらりゆらりと優雅に尻尾を揺らす余裕まであるようで、最後の一人まで逃がすつもりなどないことがその背中から読み取れる。状況は圧倒的に、ご乱心中の我らがリーダー様が優勢だった。
それでも、戦場で万が一の可能性がゼロになることは決してない。これは渡らなくてもいいはずの危ない橋だ。乱戦中に出入り口から何人かが逃げ出したのをファルコは見ている。すぐに武装を盛りに盛った増援が来ることは想像に難くない。
「うるせぇ、止めるぞ。なんか考えはないのか」
「ええ〜? うーん、羽交い締めにするなり抱きしめるなりして背中とかを撫でれば落ち着くかもしれないけど……」
「ガキか?!! チッ、この際アイツが止まるならなんでもいい。オラ、行って来い!!」
「はあ?! ちょっ、バカ言わないでよ! あんな大暴れしてるフォックスにオイラが近づけるわけないじゃないか! ファルコの方がまだ慣れてるだろ、ファルコが行ってよ!」
二人がぎゃあぎゃあと言い争う声は高い倉庫の天井に反響し、室内に響いた。自分達の声をはっきり聞き、それまであらゆる音をかき消していた喧騒がすっかり収まっていることに気付く。ファルコとスリッピーが益体もない会話をしている間に、フォックスは最後の一人を片づけてしまっていたらしい。
埃と硝煙が立ち込める中、フォックスは足元に転がる最後の一人を冷たい目で見下ろしている。正直に言ってファルコだってあまり近づきたくないのだが、スリッピーが無言でぐいぐいと押してくるので根負けして立ち上がった。
だが戦闘はもう終わっているわけで、それならファルコが行こうがスリッピーが行こうが、どちらでも良いはずである。いいように押し切られてしまったことにファルコが気付いたのは、フォックスの間合いの中にまで踏み込んでしまってからだった。
仕方がない。ファルコは大げさにため息をつくと、接近に気付いていながら一切の反応を示さないフォックスの腕を取った。
「おい、フォックス」
「……うるさい。離せ、ファルコ。こいつはお前のことを、俺の携帯食呼ばわりしたんだ。そっちの奴はスリッピーをグズでも狩れるエサだと」
「よくある悪口じゃねーか。流せよ、そんくらい」
遠い遠い祖先の習性を揶揄するのは、全種族に共通する罵倒のワイルドカードだ。特にトリ系やカエル系の種族に対して被捕食者と罵るのは使い古されて手垢だらけ、今時誰に言ったところで大したダメージは見込めない。実際に言われてみたところで腹を立てる方が難しいくらいだが、未だに興奮して毛を逆立てているキツネにそう言ったところで無駄そうだ。
どうやら相当頭に血がのぼっているらしい。スリッピーの言っていた「羽交い締めにするなり抱きしめるなりして背中とかを撫でれば」という言葉がファルコの脳裏に過る。興奮した大の男キツネを撫でて宥めすかすなど考えただけで寒気が走る行為だが、ファルコだってこの際手段を選んでいられないことはわかっていた。
ひとまず後ろから羽交い絞めを試みる。フォックスは抵抗せず、むしろ身体をファルコに預けてきた。こんな状態でもフォックスの中でファルコに対する信頼は損なわれていないのだと思うと、少し気分が上を向く。
「ケンカしに来たんじゃねえだろ、俺たちは仕事で来た。な? 落ち着け、リーダー」
「その仕事場で、売られたケンカを買ったまでだ」
「おっかねぇ顔すんじゃねえ、お前そんなガラじゃねえだろ」
「俺は相棒と親友を貶されて怒りもしない腰抜けだと?」
言ってねーだろンなこと!!!とファルコが叫ぶより先に、腕の中でフォックスの身体がすっと沈む。あ、と思った時には既に遅く、フォックスはしなやかな関節を活かして易易とファルコの腕から抜け出していた。大人しくファルコに掴まったのは仲間への信頼感からではなく、いつでも抜け出せるという傲慢な自信からだったのかもしれない。少し喜んでしまった自分が情けないやら恥ずかしいやらで、ファルコは盛大に舌打ちした。
振り返ったフォックスは緑の目をギラギラと滾らせてファルコをじっと見据えている。彼はそのまま一瞥もせず、自分の足元に倒れ伏したごろつきの腕を蹴り飛ばした。震えるその手で健気に構えられていた銃が、あらぬ方向へと転がっていく。
銃の行方には目もくれずにファルコだけを映し出す、底冷えしたフォックスの瞳は恐ろしくも美しかった。
「酷い侮辱じゃないか。それなのに怒らないのか、ファルコ」
「ああ、あれくらい屁でもねえ。だからお前もその牙をしまえ」
「……やってみせたら、わかるか?」
冷え切った目を眇め、低い声で唸るフォックスの口角が不自然に歪む。何をやるつもりだとファルコが内心首を傾げていると、ゆっくりとフォックスが距離を詰めてきた。
「おい、フォックス――」
最後まで言い切ることは許されなかった。緩慢な動きだったにもかかわらず、制止する隙は全くなかった。
子供のようにつま先立ちをしてファルコの両肩に手を置いたフォックスは、大口を開けて牙を剥くと、躊躇いもなく目の前の喉元に食らいついた。目の前の喉元、すなわちファルコの首筋に。
「…………は?」
ぞわりと背筋に怖気が走り、ファルコの身体は氷のように固まった。すぐそばのコンテナの影でスリッピーが「あちゃあ〜……」とばかりに頭を抱えているが、さすがに反応する余裕はない。
食らいつかれたといっても、フォックスの牙は肉には食い込んでいない。ただ羽毛に触れているだけだ。傷付ける意志など一切ない、甘噛みにも満たないただの接触だった。だが間近に感じるその吐息の熱さは紛れもなく捕食者のもので、身体の芯から冷えるような悪寒がファルコの全身を瞬く間に覆った。フォックスが本気で噛んでくることはあり得ない、それはわかっている。わかってはいるのだが、本能的に動けない。
直前のフォックスの言葉通り、恐らくこれは実演するフリをしているだけなのだ。携帯食やエサという謗りには、お前はこのような無体を強いられるだけの弱い存在だと侮る気持ちが含まれている。こんなことをされてもお前は怒らないのかと、フォックスはファルコに怒っていて、だからこのような暴挙に出たのだろう。
はっきり言って、ファルコからすればただの理不尽である。
ほとんど抱きつかれるような形で強制的に急所を預けさせられているこの状況に、ファルコは沸々と怒りを感じ始めていた。押し当てられた牙を伝って唾液が羽毛を湿らせるのも、ざらついた舌の感触も、何もかも振り払いたくなってくる。
(コイツ……ッ! ホンットに、マジでふっざけんなよ……!!)
引きつって声の出ない喉の代わりに心の中で絶叫しながら、ファルコは本能的な恐怖に抗い、自身の喉元をフォックスの口内へと押し付けた。羽毛の壁を越えて肉に触れる牙の感触に全身が総毛立つが、構わず更に押し付ける。牙が肉に食い込んで遂に痛みを感じ始めたその瞬間、フォックスが慌てたように身を引いた。
半歩後ろに飛び退いたフォックスが、まんまるに見開いた目でファルコを見つめる。鼓動が気になるのか胸を抑える仕草からして興奮こそ冷めきっていないようだが、その瞳には辛うじて正気の光が戻っていた。
「あ……危ないだろ! 何考えてるんだ?!」
「こっちのセリフだ! 冗談でも二度目はねえからな!!」
まだフォックスの熱が残る喉元をさすりながら、ファルコは怒鳴った。バツの悪そうな顔をして耳を垂れ下げるフォックスは、この数秒間ですっかり頭が冷えたようだ。
「ふたりとも! だ、大丈夫?」
実に気まずい二人の間に、見計らったかのようなタイミングでスリッピーの能天気な声が割り込んでくる。ペタペタと気の抜ける足音と共に駆け寄ってきたスリッピーは、ファルコとフォックスの間に挟まって二人の顔を交互に見つめ、それからへらりと笑ってみせた。
「フォックスの悪癖が出ちゃったね。ファルコ、びっくりしたでしょ」
「う……ご、ごめん……」
「今はンなこたぁどうだっていい。……注文してねぇオカワリが来るぞ」
暢気に反省会を始めようとする二人を、ファルコが鋭い声で制した。逃げ果せた数名のごろつきが、やはり増援を呼んだらしい。随分とのんびりしたお越しだが、それだけ武装をガチガチに固めている可能性だってある。
だが、そんなことすら今のファルコにはどうでも良かった。擦っても拭っても消えない喉元の熱も、一暴れすればさすがにどうにかなるはずだ。
ファルコは叱られた子供みたいな顔をしているフォックスを睨み、大仰な仕草で肩を竦めた。
「誰かさんのおかげで当初の計画もクソもねえ。どうせ交渉が決裂したらやる予定だったことだ、暴れさせろ。暴走腹ペコキツネに齧られかけた鬱憤は、このクソ溜りの殲滅でチャラにしてやる……!」
勢いに気圧されたフォックスが何か言うより先に、ファルコは風を切って飛び出していった。なだれ込んできた増援の先陣にブラスターを撃ち込み、隊列が乱れたその隙に突っ込んでいく。泥臭い肉弾戦など御免だと常日頃から文句を言っているとは思えない、凄まじく無駄のない動きだった。瞬く間に数人がその場に沈められ、無様に床を舐めている。
「うわあ……潔いくらいの八つ当たりだあ……」
先ほどまでのフォックスと遜色ない暴れぶりを見て、スリッピーは呆れ半分、感心半分に嘆息していた。行く当てを完全に失った手をただ前に伸ばすだけのフォックスを見上げ、その背中をポンポンと叩く。すっかりしょげ返ってしまっているらしいフォックスの耳は未だにぺたんと垂れ下がり、尻尾も居心地悪そうにそわそわしていた。
「フォックス」
「……ごめん」
「いいんだよ。でもオイラはともかくファルコはほら、ああやってちゃんと自分でやり返せる力があるしさ。信用してあげてよ」
「信用は……してるんだが……」
そこまで言って、フォックスは口を噤んだ。この状況で自分の口から言い訳じみた言葉を出すのが恥ずかしかったのだろうと、スリッピーは推察する。フォックスのそういうところをスリッピーは尊敬しているし、だからこそ彼の親友でいられることを誇りに思っている。が、これは今伝えるべきことではないので、その本心は長い舌で巻き取って飲み込んだ。
「ファルコの加勢に行こう、フォックス。もうこんな碌でもないトコはとっとと潰しちゃってさ、みんなでさっさと帰ろうよ」
「……ああ。うん、そうだな。ありがとう、スリッピー」
「ファルコにはあとでちゃーんと謝るんだよ!」
わかった、と苦笑交じりに頷くフォックスは、もうリーダーとしての顔を取り戻している。二人は軽くアイコンタクトを交わし、ほぼ同時にブラスターを引き抜くと、競うようにファルコの元へと駆け出した。
味方にも敵にも死者や重傷者を出すことなく、一般の会社の皮を被った武器の密造工場は完全に制圧された。すっかり静かになった建物内から重要な証拠物件をいくつか見繕い、報告を受けてすっ飛んできた軍にまとめて引き渡して、スターフォックスの任務は一段落だ。
「そういやアカデミーの頃からっつったな? お前もアレ、されたことあんのか」
「うん。オイラの時は上級生達が突っかかってきてさぁ」
グレートフォックスへと帰還する道すがら、アーウィンの通信網は先の作戦の中で見せたフォックスの振る舞いについての話題で持ちきりだった。
ヘッドセットから響くファルコとスリッピーの声を、こんなにも疎ましく思ったことがあっただろうか。非常に居心地の悪い思いをするフォックスだったが、自分が言われるだけのことをやらかした自覚はあったので、大人しく二人の話を聞いている。
「その時フォックスがさ、オイラを庇ってくれたんだよ。暴言だけじゃなくて殴られそうになったのを、フォックスが代わりに受けて、それでやり返してさ。フォックスはその時から運動神経良かったし強かったから、全員返り討ちにしちゃったんだよ。確か5人くらいいたと思うなあ。それで上級生はみんな逃げてったんだけど、でもさすがにフォックスもボロボロでさ。オイラ、フサフサの友達が他にあんまりいなかったから怪我の程度とかわからなくて。血も結構出てたし、もしかしたら死んじゃうかもって焦っちゃってさ。なのにフォックス、オイラの心配ばっかするんだよ。お前のことオモチャだなんて思ってない、って……あ、上級生がね、オイラにそう言ってきてたんだ。キツネの手慰みのオモチャに使われてる、とかなんとか。オイラはフォックスがそんなふうに考えてるなんて思ってないのにさ、フォックスは絶対違うって必死に言ってきたんだよ。痛いはずなのにオイラの心配ばっかして、オイラもどうしていいかわかんなくなっちゃって」
「……おう」
元々スリッピーは順序立てて喋るタイプではないが、メカとフォックスの事となるとそれがより顕著になる。オタク特有の早口で捲し立てられて、ファルコは話を振ったことを軽く後悔しはじめていた。今のところは甘ったるい学校生活における青春の一ページを聞かされているに等しい。
「……あの、スリッピー。その話は、もう……」
ファルコがどう話を切り上げようか思案していると、二人の通信に実に気まずそうなフォックスの声が割り込んできた。その様子から察するに、フォックスが本当に聞かせたくない話はこの先にあるらしい。つまり、ここからが面白くなるということだ。
ファルコは人の悪い笑みを浮かべ、スリッピーに続きを促した。これくらいの意地悪なら、釣りがくる程度だろう。
「えっとね、オイラはなんとかフォックスを安心させたくてさ。オモチャ呼ばわりなんてなんでもない、ってつい強がっちゃったんだよ」
「まあ……そこはわかるな。そんで?」
「そしたらフォックスがすんごい怖い顔してさ、オイラのほっぺたを噛んだんだよ。噛んだっていっても、牙を当てられただけだけど」
それでね、とスリッピーは言葉を切って軽く咳払いをした。フォックスの声真似のつもりだろうか、いつもとは違う声音を作り、当時のフォックスの言葉を一言一句違わず繰り返す。
――キツネはオモチャをこう扱う。これでもなんでもないって? なあ、スリッピー?
「……って」
「やめてくれ……本当に……」
ファルコがちょっと引こうか爆笑しようか悩んでいる間に、フォックスの情けない声がスリッピーに続いた。本気で気まずそうである。焚きつけたのはファルコだが、詳細を聞いてしまうとさすがにフォックスに同情する気持ちが湧いてきた。本人にとっては黒歴史だということが、その声だけで嫌というほど伝わってきたからだ。ある種の共感性羞恥というやつかもしれない。
「……俺は先に行く。お前たちも、気を付けて帰還してくれ」
通信ごしにもその場の微妙な空気を嗅ぎ取ったか、フォックスは一方的にそれだけ言って通信を切った。直後フォックスの乗るアーウィンが急発進し、瞬く間に遥か彼方に消えていく。通信は完全に遮断されており、ファルコやスリッピーからの受信も拒否されていた。聞きたくないし話したくない、二人だけでやってくれ――ということだろう。
「……やりすぎたか?」
「やりすぎたかも? でもさ、オイラはこの時のこと、嬉しかったんだよね。ファルコだってさ、本能的に怖かったのはあるかもしれないけど、別に嫌ではなかったでしょ?」
居たたまれず逃げ出したフォックスを無理に追おうとはせず、ファルコとスリッピーはのんびりとアーウィンを飛ばしながら雑談を続ける。
「だってさ、オイラたちのためにあんなに怒ってくれるんだよ。自分は何を言われたって平気な顔してるのにさ。それだけフォックスにとってオイラたちが大事ってことなんだし、嬉しいよね」
「……まあ……」
スリッピーの言いたいことはわかる。しかし素直に頷くのも癪な気がして、ファルコは曖昧な返事をするに留めた。フォックス本人に聞かれる心配がなくなったからだろうか、スリッピーはいつになく優しい声音で素直な気持ちを口にしているように聞こえる。それがファルコには妙に気恥ずかしく感じてしまう。
「あとさ、フォックスって普段はああじゃない? それがこう……いきなり、野性味っていうかそういうのを出されるとさぁ……」
スリッピーは照れ笑いでその先をごまかしたが、やはり言いたいことはわかってしまった。ファルコは妙に落ち着かない気持ちで自分の喉元をさする。
フォックスの一噛みに命を握られた瞬間、ファルコの心臓を跳ねさせたのは決して恐怖心だけではなかった。遠い祖先から受け継がれた被捕食者の遺伝子のせいだったのか、単純に命の危機に対する防衛反応だったのかはわからない。ただ明らかに恐怖とは違う感覚が背筋を這い上がり、身体だけではなく精神をも蝕むようなあの感覚を、ファルコはまだ鮮明に覚えている。
だがそこでファルコは思考を打ち切った。自身の首元から手を離し、そこにまだ残っている気がする熱は見て見ぬふりをする。
「しょうもないこと考えるのはやめとけ。……藪蛇だ」
「そうだねえ。オイラもキツネはともかく、ヘビは勘弁だよ」
万一にもこのチームがややこしいことになるのは避けたい。その想いはスリッピーも同じなのだろう、ファルコが話を切り上げようとすれば大人しくそれに従った。
帰ろう、とどちらからともなく言って、二機のアーウィンは加速する。
追いつくのは難しいだろうが、少しでも早く帰らなければならない。まだまだ年若いあのリーダーは、きっと自室で布団を被っていじけている。
からかい過ぎたことを一言詫びて、三人で肩を抱き寄せ合ってハイタッチの一つでもしなければならない。
全機が無事に帰還して、任務は完了するものだ。