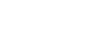聞き覚えのないイヌの鳴き声が聞こえた気がして、フォックスは耳をそばだてた。ここは大乱闘の会場に直結した控え用の別棟にある一室だ。どうも調子が悪いリフレクターの調整をするためにフォックスは残っているのだが、今日の最終試合が終わったのはもう数時間も前になる。他に残っている者などいないはずで、イヌが迷い込むような場所でもない。幻聴かと思えばそうではなかったらしく、再度はっきりとイヌの鳴き声が聞こえてきた。
ダックハントの声ではない。ルカリオでもない。それにルカリオにイヌと言うと怒られる。強いていうならウルフの声に近い気がしたが、それよりは年若く快活な印象の声だったと思う。まさかウルフ恋しさに、あやふやな記憶で声を再現してしまっているのかと一瞬考えて、フォックスは失笑した。与太話にしても笑えない。
そもそも幻聴ではなさそうだし、扉の外にはっきりと何かの気配がする。あれこれ考えるよりは見た方が早いだろうと、フォックスはリフレクターを机の上に置いて扉を開けた。
「ワンッ!」
「……本当に知らないやつじゃないか」
扉を開けると、そこには一匹の犬――というより狼だろうか。緑がかった珍しい毛色を持つ大柄な獣が、長いしっぽをぶんぶんと振り回してフォックスを見上げていた。思わず漏れた独り言の通り、見覚えのない狼だ。妙に表情豊かなその狼は、フォックスを見るなり嬉しそうに口を開けると、その場で跳ねながらくるくると回った。動物の言葉はわからないフォックスだが、狼の表情と仕草から察するにどうやら懐かれているらしい。
狼は開け放たれた扉を潜ろうとはせず、ひとしきりくるくる回った後はその場にお座りをしてフォックスを見上げている。ちらちらと視線が部屋の中に向かうので興味はあるようだが、フォックスの許可なく部屋の中へ入るつもりはないらしい。躾がかなり行き届いている印象だった。
「……入るか?」
「ワンッ!!」
試しに尋ねてみると、狼は嬉しそうな声を上げ、立ち上がってまたその場でくるくると跳ねた。二回りしてからフォックスの横を通り、狼は部屋の真ん中を陣取ってリラックスした体勢で座り込む。どうやらこちらの言葉がある程度は通じるようだ。扉は開け放したまま、フォックスも狼の後に続いて室内に戻った。
「それで、お前はどこの誰なんだ?」
「ワンッ! ワンワンッ!」
「……さすがにわからないな。クリスタルなら通訳してくれただろうか」
「ウゥ~……」
フォックスがぼやくと、何故か狼は不機嫌に唸り出した。言葉を理解しているようだから、わからないと言ったのが気に食わなかったのかもしれない。ごめんな、と頭を撫でてやればイヤイヤと振り払われてしまったが、その尻尾はぶんぶんと大きく振られていたので、本気で嫌がられているわけではなさそうだった。
そういうことなら、ともう一度頭を撫でてやると、今度は抵抗されなかった。床に膝をついて目線を合わせ、両手で頬を包んでわしゃわしゃと撫でれば、気持ちよさそうに狼は目を細める。こうも素直に反応されるとよりいっそう愛らしく感じるもので、フォックスは耳や頭も含めた狼の顔中を更に撫で回した。
「……ん?」
ふと指先に固いものが当たり、フォックスは手を止めた。異質な感触の正体は、狼の耳に付けられた青い耳飾りだった。どうやらピアスのようで、針が耳の薄い肉を貫通している。世界によっては動物愛護なんちゃらやらの法だかに引っ掛かりそうだ。だがフォックスが引っ掛かったのはそこではなかった。その青いピアスに、フォックスは見覚えがあったのだ。
どこだろう。どこかで見たことがある。数秒考えて思い出したのは、大きい方のリンクの、あの特徴的な長い耳だった。その耳にいつも付いているピアスと今この狼の耳についているピアスは、フォックスの記憶が正しければまったく同じ形状で同じ色をしている。
「え……ってことは、お前、もしかしてリンクなのか?」
「! ワンッ!!」
信じがたい気持ちで呟けば、更に信じがたいことに狼が嬉しそうに吠え、立ち上がってその場でくるくると回り始めた。どうやらこれは、この狼が嬉しい時にする行動らしい。素早く何回転かした狼は突然動きを止めたかと思うと、勢いよくフォックスに飛び掛かってくる。片膝を立てていたところに思いきり体当たりを食らう形になり、フォックスはそのまま床に転がった。すっかり興奮状態にあるらしい狼が息を荒げながら、転がったフォックスの頬をべろりと舐める。
リンクがこんなことをするだろうか?
顔を好き放題舐め回されながら、フォックスは遠い目をして考える。そもそもの話だが、リンクのような『人間』が突然狼の姿になること自体――いや、そういえば今回は突然竜になるファイターだって参戦している。それにフォックスは、前回の大会の時にリンク自身から『狼の姿になるハイラルの勇者』の話を聞いていた。この人懐っこいというレベルでは済まされない狼がリンクかもしれない、という仮定はそこまで荒唐無稽でもないだろう。
そこでフォックスの思考は振り出しに戻った。この狼がリンクだと仮定した場合、行動があまりにも普段のリンクとはかけ離れている。身体の作りが変われば精神も引っ張られるとはよく聞く話だが、ここまで豹変するものだろうか。リンクはどちらかといえばフォックスと同じく常識人枠で、自由に爆走する問題児たちのストッパー兼ツッコミ役を担う存在だったはずだ。それが今は、狼というよりは大型犬さながらにフォックスに飛びついては離れ、飛びついては離れを繰り返すご機嫌なワンコと化している。あるいは常識人故に日頃の鬱憤が溜まっていて、ここぞとばかりにそれを発散している最中なのかもしれないが。
「リンク、リンク。わかった、わかったから落ち着いてくれ」
「ワンッ!」
涎でべたべたになった頬を拭いながら声を掛けると、即座に元気な声が返ってくる。が、尻尾は激しく振られ続けており、フォックスに軽く体当たりを繰り返す動きも止まることはない。落ち着く気がないのか、それとも彼にとってはこれでも落ち着いている方なのか。後者だとすればヒートアップした時はどうなるのかと末恐ろしい。
そんなことを考えてしまったのが引き金となったのかもしれない。動物、特にイヌ科の生き物は感情を敏感に察知するというのは有名な話だ。
狼は起き上がろうとするフォックスの鼻先に自分の鼻先を寄せると、おもむろに前足パンチを繰り出した。軽いジャブ程度のパンチでも、中途半端な態勢を突き崩すには十分だ。思いきり肩を押されたフォックスが踏みとどまろうとしてバランスを崩し、その場でうつ伏せに倒れこむ。その一連の動きが興奮を誘発したか、狼はいっそう嬉しげに尻尾を振りながら、倒れたフォックスに伸し掛かった。
「ちょっ、リンク、やめろって……!」
首を中心に上半身を両前足でがっつりと押さえられ、そのまま耳を甘噛みされる。床が綺麗に掃除されていて良かった、とフォックスは思った。引き倒された先であるフローリングは、土足が許されている場所だということを考えなければ冷やっこくて気持ちがいい。上から伸し掛かる体重がくすぐったくて、どこか懐かしい感覚だ。やめろと口では言ったものの、フォックスに本気で抵抗する気はなかった。
フォックスの種族は、遠い祖先がイヌ科の動物であると言われている。そのためか子供同士はこういったじゃれ合いをするのだが、それはあくまで子供同士の遊びである。大人はやらないし、やったとしたら少し意味合いが変わってしまう。今のリンクがどこまで人としての理性を残しているのかわからないが、彼があくまで狼としてこのじゃれ合いを仕掛けてきているのなら、狐らしくやり返しても問題はないのかもしれない。だがそうではなかったとしたら、狼ではなくリンクに対してやり返すことになるのなら、それは少し気恥ずかしいというのがフォックスの本音だった。
口だけでろくな抵抗をしないフォックスが、狼はどうやら気に食わないらしかった。口にすっぽり含んだフォックスの耳を食みながら、時々軽く引っ張ってくる。首に回された前足が、床をたしたしと不満げに蹴った。「ちゃんと遊べ」と言いたいようで、フォックスは苦笑する。うつ伏せの状態から仰向けに姿勢を返すと、狼はまた嬉しそうに尻尾を振った。いよいよ遊んで貰えると思って気色ばんだらしい。しかしフォックスが宥めるようにその顔を撫でると、すぐに不満げな声でぐるぐると唸り出した。
「お前は若いからいいけど、俺がこの歳でやるのはちょっとな」
「ウゥ~……!」
「この返事は不合格、と。わかった、わかったよ」
このままではじゃれつきが喧嘩に発展しかねない唸りっぷりで、フォックスは遂に白旗を上げた。人間に戻ったリンクがこのことを覚えていないといいんだが、と心の中で祈りながら、油断しきった狼の首を狙ってそのまま床に引き倒す。されたことをそっくりそのままやり返すくらいなら、後でどうとでも言い訳が効くだろう、という打算が働いての行動だった。自分の下でごろんと仰向けに転がった狼を見下ろすと、その耳につけられた青い耳飾りが目に入る。
イヌ科同士のじゃれ合いならともかく、リンク相手にするのはと躊躇していたフォックスが、それに狙いを定めるのは明らかに矛盾している。だが自分の手で引き倒した相手が眼下にいる状況は、存外フォックスの中の本能に働きかけるものがあったらしい。引き倒されても尚挑発的に向けられた視線を無視して、フォックスは狼の耳ごとその耳飾りを咥え込んだ。口蓋に耳の細やかな被毛の柔らかさを、舌の上に耳飾りの無機質な硬質さを感じる。狼は最初こそ前足でフォックスの身体を蹴って抵抗していたが、フォックスが口に含んだ耳を甘噛みし、耳飾りをべろりと舐め上げた瞬間にすっかり大人しくなってしまった。
……さすがに、これはダメなんじゃないか?
食われることを覚悟した草食獣のようになってしまった狼の耳を甘噛みしながら、フォックスはふと我に返った。この状況を、たとえばファルコに見られたとして、言い訳出来るだろうか。出来るわけがない。考えるまでもないことだ、他の誰に見られても言い訳のしようがないだろう。そうなると、次に湧き出てくるのは焦りだった。何しろここは試合以外ではほぼ使われることがないとはいえ、ファイターであれば誰でも出入り自由な場所だ。加えて部屋の扉は開けっ放しである。今この瞬間、誰に見られてもおかしくない状況だった。
ひとしきり焦った後は、すっかり無抵抗な狼に対して沸々と不満が湧いてきた。フォックスが無抵抗だった時は「真面目にやれ」とせっついて来たくせに、いざ相手をしたらこれである。どうぞお召し上がりくださいと言わんばかりの無抵抗さは、フォックスが目を背けていたかった違う意味でのじゃれ合いを彷彿とさせて、それに気づいてしまったら猛烈に居心地が悪くなってきた。
せめてもの抵抗か八つ当たりか、自分でも判然としないままフォックスは強めに狼の耳を一噛みして、身体を起こした。フォックスをじっと見上げてくる狼の目から、何を考えているのか読み取ることは出来なかった。淫靡な色が乗っていないだけマシだと考えるべきだろうか。これでそんな目を向けられてしまったら、いよいよ居心地が悪いなんてものではなくなってしまう。
「ごめんな。俺はもう大人だからさ、遊び方は忘れたみたいだ」
言い訳じみた言葉で謝りながら、フォックスは狼の耳を撫でた。先ほどフォックスが噛んでいた、あの耳だ。痛くなかったかと尋ねると、狼は問題ないとばかりに首を振り、それからゆっくりと起き上がった。
物言いたげな視線が真正面から向けられる。狼は床に座ったままフォックスを見上げるばかりで、あんなに忙しなかった尻尾が今はぴくりとも動かない。ピンと立てられた耳を彩る耳飾りの青より更に鮮やかな双眸に、このまま射られてしまいそうだと思った。
狼はじっとフォックスを見つめたまま、ゆっくりと一歩踏み出して、鼻先をフォックスの鼻先へと押し付ける。
控え目に出された舌がフォックスの鼻と口元を一度だけなぞり、それからゆっくりと離れていった。
「……それは、どういう意味の行動だ? リンク」
低い声でフォックスが尋ねても、狼からの返事はなかった。ただ、その口角がまるで人のように、歪つな笑みを模った気がした。